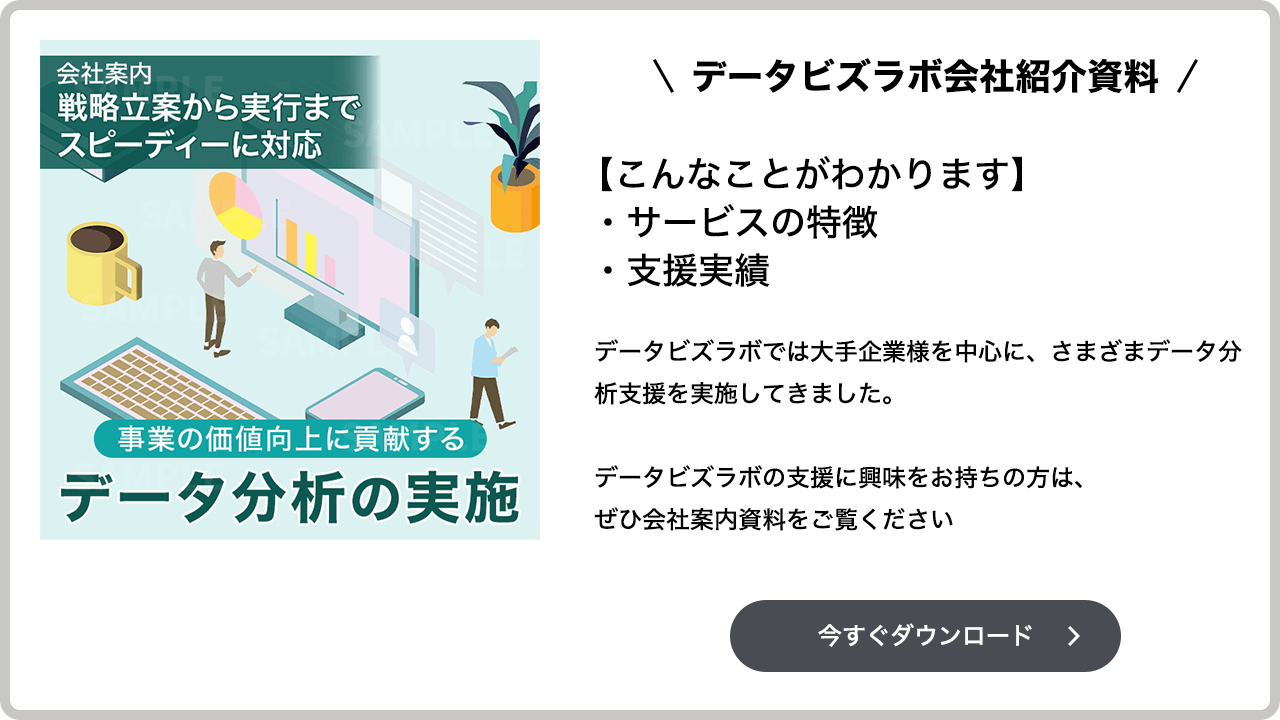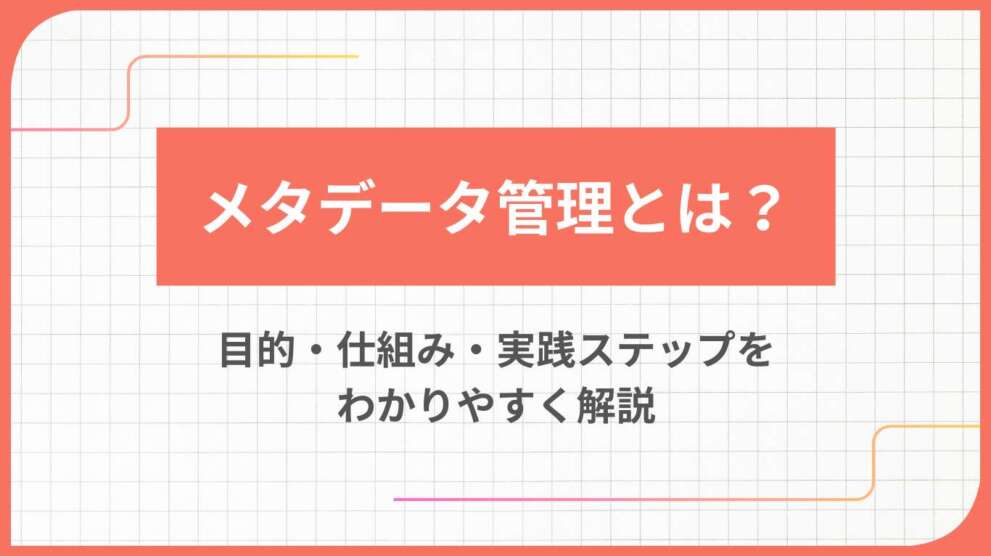
近年、企業が扱うデータ量は急速に増え、複数のシステムや部署に同一テーマのデータが分散して管理されるケースが増えています。「必要なデータがどこにあるかわからない」「同じ指標なのに部署ごとに数値が違う」といった混乱を経験した方も多いでしょう。背景には、データそのものではなく「データに関する情報」が整理されていないことがあります。
本記事では、データ活用を支える基盤である「メタデータ管理」に注目し、その目的・仕組み・導入ステップをわかりやすく解説。組織全体で信頼できるデータ環境を築きたい方に向けて、実践的なポイントを紹介します。
目次
メタデータ管理とは
メタデータ管理とは、データそのものではなく「データに関する情報(=メタデータ)」を整理・管理することです。データの出所や意味、形式、更新履歴などを体系的に記録し、誰もが活用できる状態に保つ仕組みを指します。
メタデータを適切に管理することで、企業は自社が保有する膨大なデータの構造や意味を正しく把握し、再利用や分析に生かせます。たとえば、同じ「売上データ」であっても、作成部署や更新日時、算出ルールが明確であれば、信頼性の高い分析が可能です。
また、メタデータ管理はデータガバナンスやデータカタログの基盤としても欠かせません。組織全体でデータの意味や定義を共有し、透明性の高いデータ活用を実現するための中核的な役割を果たすのです。
メタデータの意味と主な種類
メタデータとは、データに関する詳細を表す「データを説明する情報」だと説明しました。ファイル名や作成日、作成者などの基本情報から、データの定義、形式、保存場所、更新履歴といった付随情報までを含みます。つまり、メタデータはデータを正しく理解し、活用するための「説明書」のような役割を持つのです。
メタデータには、主に次の3種類があります。
- ビジネスメタデータ:データの意味や目的、業務上の定義、責任部門などを示す。
- テクニカルメタデータ:テーブル構造やカラム名、データ型、ETL処理やデータフローなど、システム上の構造や仕様を記述する。
- オペレーショナルメタデータ:更新日時、アクセス権限、利用頻度、変更履歴など、運用・管理に関する情報を示す。
これらを統合的に管理することで、業務部門とデータ部門が同じ視点でデータを理解できるようになり、整合性の確保や活用の効率化につながります。
メタデータ管理が必要な理由
ここまで、メタデータの意味や種類を見てきました。メタデータは単なる「補足情報」ではなく、データを理解し活用するための重要な土台です。では、なぜ企業がメタデータを組織的に管理する必要があるのでしょうか。
データ量が増え、分析やAI活用の機会が広がる中で、メタデータの整理はもはや「あると便利なもの」ではなく「なくてはならないもの」になっています。次は、メタデータ管理が必要とされる4つの主な理由について見ていきましょう。
データの所在・意味を明確化し、属人化を防ぐため
メタデータを管理することで、社内に散在するデータの「どこに何があるのか」を明確にできます。部署ごとに異なるフォルダ構造や命名ルールで保存されているデータも、メタデータを整理することで全体像を把握しやすくなります。
また、データの意味や作成経緯、責任者などを明確にしておくことで、特定の担当者にしかわからない「属人的な運用」の防止が可能です。担当が変わっても同じ情報を再利用できるようになり、業務の継続性と効率が向上します。
データを組織の資産として共有し、誰もが同じ基準で理解できる状態をつくる。それがメタデータ管理の第一の目的です。
データ品質の維持・改善を継続的に行うため
メタデータ管理は、データ品質を継続的に高めるための基盤になります。データの定義や入力ルール、更新履歴を明示しておけば、誤入力や重複登録など、データ入力・管理プロセスで生じる品質劣化を抑えることが可能です。
また、データの変遷や修正内容が追跡できることで、問題が起きた際に原因を特定しやすくなります。たとえば「いつ、誰が、どのデータを変更したか」を把握できれば、改善策の検討がスムーズに進むでしょう。
品質の維持は一度整えれば終わりではありません。メタデータを活用して監視・見直しを繰り返す仕組みが、データ基盤の信頼性を支えるのです。
データ利活用・分析・AI導入の前提としての透明性を確保するため
データを有効活用するためには、「どのデータを使えば良いのか」「そのデータは信頼できるのか」が明確であることが欠かせません。メタデータ管理はそのための「透明性」を担保します。
分析担当者やAI開発者がデータの由来や定義を正確に理解できれば、誤った判断や学習のリスクを減らせます。データの意味や構造が整理されていれば、異なるシステム間での連携や統合も容易です。
つまり、メタデータ管理はAIやBIなどの高度なデータ活用を支える基礎であり、信頼できるデータドリブン経営を実現するための前提条件なのです。
コンプライアンス対応(個人情報保護・トレーサビリティ)を支援するため
近年、個人情報保護法やGDPRなどの規制が強化され、企業にはデータの扱いに関する説明責任が求められるようになりました。メタデータを整備しておけば、個人データを含む情報の取得元・利用目的・保存期間などを体系的に把握でき、法令遵守体制の構築を実務的に支援できます。
さらに、データの変更履歴や利用履歴を追跡できる状態にしておくことで、万が一トラブルが発生しても迅速に経路を特定できます。こうした「トレーサビリティ(追跡可能性)」は、監査対応やリスク管理のうえでも不可欠です。
コンプライアンス対応を確実に行ううえで、メタデータ管理は単なる管理作業ではなく、組織の信頼を守るための防衛線といえるでしょう。
メタデータ管理の仕組みと構成要素
ここまで、メタデータ管理の目的や必要性を見てきました。では、実際にメタデータをどのように整理・運用していくのでしょうか。その中心には、メタデータを一元的に保管し、利用できるようにする仕組みがあります。
メタデータ管理の仕組みは、大きく「保管」「検索・閲覧」「収集」「運用統制」の4つの機能で構成されます。これらが連携して動くことで、データの信頼性と利便性を両立できるのです。次は、それぞれの構成要素について詳しく見ていきましょう。
メタデータリポジトリ
メタデータリポジトリは、すべてのメタデータを一元的に集約・管理する中核的なデータベースです。ここには、データの定義、構造、出所、更新履歴、責任者などの情報が体系的に登録されます。
リポジトリがあることで、どの部署やシステムのデータであっても、共通の基準で把握・比較できるようになります。いわば、組織全体の「データ辞書」として機能する存在です。
また、リポジトリは他システムとも連携しやすく、ETLツールやBIツール、データ統合基盤などから参照・更新できるように設計されるケースもあります。これにより、業務フロー全体で一貫したデータ管理が実現します。
データカタログ
データカタログは、メタデータリポジトリに登録された情報を、ユーザーが検索・閲覧できる形で提供する仕組みです。誰でも必要なデータの意味や利用可能範囲を確認できるため、業務部門や分析担当者の「探す時間」を大幅に減らせます。
また、データカタログには検索機能やタグ付け機能が備わっており、キーワードやカテゴリで簡単に目的のデータを探せます。これにより、専門知識がなくても直感的にデータを扱える環境の整備が可能です。
さらに、データの利用頻度や評価、コメントなどを共有できる仕組みを持つツールもあり、社内でのデータ活用文化の促進にもつながります。
メタデータ収集ツール
メタデータ収集ツールは、システム内外に散らばるメタデータを自動的に収集し、リポジトリへ登録・更新する役割を担います。ETL(Extract, Transform, Load)ツールやAPI連携を利用して、定期的に最新情報を反映する仕組みです。
この自動収集によって、手作業での登録・更新ミスを防ぎ、運用負荷を軽減できます。データ量が増えるほど、手動管理では精度やスピードに限界があるため、自動化の仕組みは欠かせません。
また、ツールによっては、データソースやスキーマの変更を定期的またはリアルタイムに検知し、リポジトリへ自動反映する機能を備えています。これにより、データ更新の遅れや不整合を防ぐ効果があります。結果として、リポジトリ内の情報を常に最新・正確な状態に保てるのです。
ワークフロー管理・承認プロセス
メタデータの変更や公開には、承認プロセスを通すことが重要です。ワークフロー管理の仕組みを導入することで、誰がどの情報を変更・登録したのかを記録し、適切なレビューや承認を経て公開できます。
これにより、誤った定義や不完全な情報が組織全体に広がることを防げます。特に、業務システムや分析基盤など、複数部門が同じデータを使う環境では、変更管理の透明性が欠かせません。
さらに、承認履歴やステータスを可視化することで、データ変更の流れを誰でも追跡できるようになります。統制と透明性を両立することが、信頼できるメタデータ管理体制を築く鍵です。
メタデータの種類と分類
ここまで、メタデータ管理の仕組みや構成要素を見てきました。次に押さえておきたいのが、メタデータの「種類と分類」です。メタデータにはいくつかのタイプがあり、それぞれが異なる役割を担っています。
これらを正しく区別し、目的に応じて管理することで、データの信頼性と活用の幅を高められます。次は、メタデータの主な3つの分類について見ていきましょう。
技術的 / テクニカルメタデータ:データ構造・テーブル・カラム・データ型など
技術的メタデータは、データがどのような構造で保存されているかを示す情報です。データベースやシステムの内部構成を理解するうえで欠かせない要素です。
たとえば、テーブル名やカラム名、データ型、制約条件、インデックス設定、スキーマ構造、ファイル形式、データフローなどが該当します。これらの情報を把握しておくことで、データ間の関係性や依存性を明確にでき、効率的なシステム設計やトラブルシューティングに役立ちます。
また、ETL処理やAPI連携などを行う際の基礎となるのも、技術的メタデータです。つまり、データを動かす仕組みを理解するための技術的な裏付けとなるのです。
業務 / ビジネスメタデータ:ビジネス上の意味・定義・責任部門など
業務メタデータは、データがどのような意味や目的を持ち、どの業務で使われるのかを明らかにする情報です。組織内でデータの意味づけや使い方を統一するために重要な役割を果たします。
たとえば、「売上金額」「顧客ID」「取引日」などの項目が、どの業務プロセスでどのように定義されているか、誰が責任を持って管理しているのかを明記します。これにより、同じデータでも部署や担当者によって意味が異なるといった混乱を防止可能です。
業務メタデータが整備されていると、経営層や現場の担当者が共通の基準でデータを読み解けるようになります。結果として、業務改善や意思決定のスピードが高まり、データ活用の成果が安定します。
運用 / オペレーショナルメタデータ:更新履歴・アクセス権限・利用頻度・変更履歴など
運用メタデータは、データがどのように管理・利用されているかを記録する情報です。主にシステム運用やセキュリティ、監査の観点から重要とされます。
代表的な要素として、データの更新日時、更新者、アクセス権限、利用頻度、エラーログ、処理時間、変更履歴、バックアップ状況などがあります。これらの情報を記録しておけば、問題発生時の原因追跡や責任の明確化も容易です。
また、運用メタデータは、データの利用状況を可視化するうえでも有効です。どのデータがよく使われているのかを把握できれば、不要データの整理や保守コストの削減にもつながります。
統合的に管理することで、技術部門と業務部門の橋渡しが可能になる
技術・業務・運用の3つのメタデータは、個別に存在するだけでは十分な価値を発揮できません。情報を統合的に管理することで、組織全体のデータ活用力を大きく高められます。
技術的メタデータによってデータ構造を把握し、業務メタデータでその意味を共有し、運用メタデータで品質と透明性を担保する。これらが連携して初めて、技術部門と業務部門の橋渡しが実現するのです。
このように、メタデータを横断的に管理することは、データガバナンスを強化し、全社的なデータ利活用の基盤を築くうえで欠かせないステップといえるでしょう。
メタデータ管理の導入ステップ
ここまで、メタデータの種類や仕組みを整理してきました。では、実際にメタデータ管理を導入するには、どのような手順で進めればよいのでしょうか。やみくもにツールを導入しても、運用ルールや目的が明確でなければ長続きしません。
メタデータ管理は、段階的に進めることで効果が高まります。次は、導入から定着までの5つのステップについて見ていきましょう。
STEP1:現状のデータ資産を棚卸し、管理対象を特定
最初のステップは、社内にどのようなデータ資産が存在しているのかを把握することです。各部署やシステムで管理されているデータを洗い出し、どのデータセットについてメタデータを管理するかを整理します。
この段階で重要なのは、「すべてのデータを一度に管理しようとしないこと」です。まずは、経営判断や分析など業務への影響が大きいデータ群から対象を絞り、優先順位をつけて着手します。
こうして現状の可視化と優先付けを行うことで、後続の設計や運用フェーズがスムーズに進みます。
STEP2:メタデータ項目(定義・更新頻度・責任者など)を設計
次に、どのような情報をメタデータとして記録するかを設計します。たとえば、データ名、定義、作成者、更新頻度、責任部門、データ型などの項目を整理します。
この設計段階では、業務部門とデータ部門が協力し、業務上の意味とシステム的な仕様の両面から項目を検討することが大切です。業務で使う言葉とシステム上の構造を対応づけることで、誰にとってもわかりやすいデータ辞書を作れます。
また、将来的な拡張性も考慮し、あとから新しい属性やルールを追加できるよう柔軟な設計を意識しましょう。
STEP3:メタデータ収集方法(自動・手動・API連携)を決定
次は、設計した項目をどのように集め、維持していくかを決める段階です。メタデータの収集方法には、各システムのスキーマ情報やログなどのメタデータを自動取得する方法、担当者が手動で登録する方法、APIやETLツールを介して連携する方法などがあります。
自動化できる部分は積極的に自動化し、手動入力が必要な部分はフォーマットやルールを定めておくのが理想です。たとえば、テーブル構造やカラム情報は自動取得し、業務的な定義や責任者情報は担当者が補完する、といった分担が効果的です。
収集後は、定期的な更新スケジュールを設けることで、古い情報が残らないように管理します。
STEP4:リポジトリやデータカタログを構築・運用
収集したメタデータを一元的に管理するための基盤を構築します。中心となるのが「メタデータリポジトリ」であり、ここに整理された情報を格納していきます。
加えて、利用者が必要なデータを探しやすくするために「データカタログ」を導入すると効果的です。検索機能やタグ付け機能を備えたカタログを使うことで、業務担当者でも直感的に目的のデータを見つけられるようになります。
この段階では、利用者の使いやすさを意識した設計がポイントです。ツールを入れるだけでなく、誰がどのように使うかを具体的に想定しながら運用ルールを整えることが大切です。
STEP5:継続的な品質監査と更新プロセスの確立
最後に、メタデータを最新かつ正確な状態で保つための仕組みを整えます。どんなに整備されたリポジトリでも、情報が更新されないままでは価値が薄れてしまいます。
更新サイクルや承認フローを明確にし、定期的にメタデータの品質をチェックする体制を構築しましょう。たとえば、半年ごとにメタデータレビューを実施し、不要データの削除や定義の見直しを行うといった取り組みが有効です。
こうした継続的な運用を通じて、メタデータ管理は単なる一時的なプロジェクトではなく、組織文化として根付いていきます。
メタデータ管理のメリット
ここまで、メタデータ管理の導入手順を確認してきました。では、実際にメタデータを整備・運用することで、どのような効果が得られるのでしょうか。メタデータ管理は単なる情報整理ではなく、業務効率やデータ品質、ガバナンス強化など、企業全体に幅広いメリットをもたらします。
次は、メタデータ管理によって得られる4つの主なメリットについて見ていきましょう。
データ探索の効率化:必要なデータをすぐに見つけられる
メタデータ管理の大きな利点は、必要なデータを素早く見つけられるようになることです。従来は「どのシステムに何のデータがあるのか」がわからず、担当者に確認しながら探すことも少なくありませんでした。
データカタログを通じてメタデータが整理されていれば、キーワード検索やカテゴリごとに目的のデータを簡単に見つけることが可能です。業務部門の担当者でも、データ部門に依頼することなく自ら必要な情報を探せるようになります。
結果として、分析やレポート作成などのスピードが上がり、組織全体での意思決定が迅速になります。
データの再利用促進:既存データの活用機会を最大化
メタデータが整備されていると、既存のデータを別の目的で活用しやすくなります。どのデータがどんな意味を持ち、どの部署で管理されているのかが明確であれば、新たにデータを作り直す必要がありません。
たとえば、営業部が蓄積した顧客データを、マーケティング部門がキャンペーン分析に活用する、といった連携がスムーズになります。これにより、データの重複管理を防ぎ、コスト削減にもつながります。
さらに、社内でデータの可視化が進むことで、「使えるデータがあるなら活用しよう」という文化が根づき、組織全体のデータ活用力が高まるでしょう。
データ品質とガバナンスの強化:整合性・透明性を担保
メタデータを体系的に管理することで、データの整合性と透明性を高い水準で保てるようになります。データの定義や管理ルールを明確にすることで、「同じ項目名なのに中身が違う」といった混乱を防止できます。
また、メタデータには更新履歴や責任者情報を紐づけて記録できるため、誰がいつどのようにデータやその定義を変更したのかを追跡可能です。これにより、データの信頼性を客観的に評価でき、品質向上の取り組みを継続的に行えます。
ガバナンスの面でも、明確なルールのもとでデータを運用できるようになり、全社的な統制の基盤として機能します。
監査・法令対応の円滑化:データの由来や利用履歴を追跡可能
メタデータ管理は、監査対応や法令遵守の面でも大きな効果を発揮します。データの取得元、利用目的、保存期間、共有範囲などがメタデータとして明示されていれば、監査や調査において迅速に説明責任を果たせます。
また、データの流れや利用履歴(データリネージ)を把握できるため、万が一の情報漏えいや誤利用の際も原因の特定が容易です。個人情報保護法やGDPRなどの規制対応にも役立ち、企業のリスク管理体制を強化できます。
このように、メタデータ管理は業務効率の向上だけでなく、法的・社会的な信頼性の向上にもつながる取り組みなのです。
メタデータ管理の課題と注意点
ここまで、メタデータ管理の仕組みやメリットを紹介してきました。しかし、導入や運用の段階では多くの企業が共通の課題に直面します。メタデータを整備すれば自動的にデータ品質が上がるわけではなく、運用体制やルールの整備が欠かせません。
次は、メタデータ管理を進める際に注意しておきたい4つの課題と、その背景について見ていきましょう。
メタデータ登録・更新の運用負荷が高い
メタデータ管理の最初の壁は、登録や更新にかかる運用負荷の高さです。特に導入初期は、既存のシステムやファイルからメタデータを洗い出す作業に時間と手間がかかります。
一度整備しても、データが更新されるたびにメタデータも更新が必要になります。これを手作業で続けると、担当者の負担が増え、徐々に運用が滞るケースも少なくありません。
この課題を解決するには、収集や更新を自動化する仕組みを導入することが重要です。ETLツールやAPI連携を活用し、できるだけ人の手を介さずにメタデータを更新できる体制を整えることが求められます。
業務部門とデータ部門の間で定義や責任範囲が曖昧になりやすい
メタデータには、システム的な情報だけでなく、業務上の意味や定義も含まれます。そのため、データ部門と業務部門のどちらがどの範囲を管理するのかが曖昧になることがあります。
たとえば、データ項目の「定義」は業務部門が把握しているものの、「実際の構造」や「格納先」はデータ部門でしかわからないような場合です。責任の所在が不明確なままだと、更新漏れや定義の重複が発生しやすくなります。
このような問題を防ぐには、メタデータの項目ごとに管理責任者を明確にし、ガイドラインとして文書化しておくことが効果的です。業務・IT双方が共通のルールで運用できる状態をつくることが理想です。
管理対象が増えるとツール運用コストが上昇する
メタデータ管理の範囲を広げていくと、データ量やシステム数の増加に伴って、ツールのライセンス費用やインフラ運用コストが上昇する傾向があります。特にクラウド型ツールでは、利用ユーザー数や登録オブジェクト数に応じた課金モデルが採用されている場合が多く、想定よりも費用が膨らむケースも少なくありません。
特に、複数のデータソースを統合して管理する場合、ツール間連携やデータマッピングの設定に追加コストがかかることがあります。
この課題を避けるためには、初期段階で「どの範囲をどのツールで管理するのか」を明確にし、段階的にスコープを拡大することが重要です。必要以上に広げすぎず、運用負荷と効果のバランスを見極めながら進める姿勢が求められます。
属人化を避けるため、標準ルールと自動化の両立が必要
メタデータ管理が特定の担当者の知識や経験に依存してしまうと、担当交代や組織変更の際に運用が止まるリスクがあります。属人化を防ぐには、標準ルールの策定と自動化の仕組みづくりが欠かせません。
標準ルールとしては、命名規則や登録手順、承認フローなどを明文化し、誰が運用しても同じ品質で管理できる状態を目指します。これに加えて、ツールやスクリプトによる自動収集・更新を組み合わせることで、ルールを実務に定着させることが可能になります。
「人に依存しない運用」を実現することは、メタデータ管理を長期的に継続するための最大のポイントといえるでしょう。
メタデータ管理を成功させるポイント
ここまで、メタデータ管理の課題や注意点を整理してきました。では、実際にメタデータ管理を定着させ、効果を最大化するためには何が重要なのでしょうか。導入に成功している企業は、仕組みやツールの導入だけでなく、組織体制や文化づくりにも力を入れています。
メタデータ管理を形だけで終わらせないためには、業務とITの両面から運用を支える仕組みづくりが欠かせません。次は、メタデータ管理を成功に導く4つのポイントについて見ていきましょう。
業務・IT両面からガバナンス体制を構築する
メタデータ管理の成否を分けるのは、業務部門とデータ部門が連携できるガバナンス体制の構築です。業務部門はデータの意味や利用目的を把握し、データ部門はシステム構造や管理手法を理解しています。この両者が協力し、共通のルールのもとでメタデータを運用することが理想です。
具体的には、データオーナーやデータスチュワードといった役割を明確にし、それぞれの責任範囲を定義します。データオーナーが戦略的な方針を示し、スチュワードが日常の運用を担うことで、管理と活用のバランスを取ることが可能です。
また、データガバナンス委員会などの横断的な組織を設けることで、全社的な合意形成や優先順位の調整を行いやすくなります。
自動収集・更新の仕組みを整え、属人的運用を排除する
メタデータ管理の運用を人に依存させないためには、自動化の仕組みを取り入れることが重要です。対応するツールや設定によってはデータの更新や構造の変更を自動検知し、メタデータに反映できます。これにより、運用負荷の大幅な軽減が可能です。
ETLツールやAPI連携を活用することで、各システムが提供するスキーマ情報やログといったメタデータを自動収集し、最新の状態を維持できます。こうした自動化の仕組みを導入することで、担当者の作業ミスを防ぎ、情報の正確性を保てます。
一方で、すべてを自動化するのではなく、業務的な定義や管理方針などは人の判断で整備しなければなりません。自動化と人の確認をうまく組み合わせることで、柔軟かつ安定した運用が実現します。
メタデータを「見せる」ことでデータ活用文化を醸成する
メタデータは管理するだけでなく、社員が「見て使う」ことで価値を発揮します。データカタログを活用し、権限の範囲で誰でも簡単にデータの内容や定義を確認できる環境を整えることが、データ活用文化の第一歩です。
社員が自らデータを探し、理解して活用できるようになると、データ活用が現場レベルで広がっていきます。メタデータをオープンにすることで、「使えるデータを共有しよう」「自分たちで分析してみよう」という意識が育まれるでしょう。
さらに、データの利用状況や人気データを可視化する仕組みを設ければ、データの価値がより明確になり、組織全体のモチベーション向上にもつながります。
データリネージ(流れ)や利用履歴を可視化し、信頼性を高める
メタデータ管理を効果的に活用するためには、データの流れや利用履歴を可視化することが欠かせません。データリネージとは、データがどこから来て、どのように加工・統合され、どこで使われているかを示す情報です。
リネージを可視化することで、データの由来を明確にし、分析結果の信頼性を高めることが可能です。また、誤ったデータが発見された場合でも、影響範囲をすぐに特定でき、修正対応が迅速になります。
加えて、利用履歴を追跡できるようにすることで、どの部署がどのデータを使っているかが把握でき、重複作業の削減やアクセス管理の強化にもつながります。こうした「見える化の仕組み」が、データへの信頼を組織全体で高める鍵です。
まとめ|メタデータ管理で探せる・信頼できるデータ環境をつくる
メタデータ管理は、データを「探せる」「理解できる」「信頼できる」状態にするための基盤です。単なる整理作業ではなく、データの品質を保ち、全社で共有・活用できる仕組みをつくる取り組みといえます。
データ活用が経営の中心にある今、メタデータを整備することは「後回しにできない投資」です。データの定義や更新履歴を可視化することで、分析の再現性と精度が高まり、意思決定のスピードも向上します。さらに、AI導入やコンプライアンス対応といった次の段階にもスムーズに移行できる基盤を整えられます。
まずは、身近な範囲からデータ資産を棚卸し、メタデータの整備に取り組むことが大切です。小さく始め、継続的に運用ルールを磨いていくことで、「信頼できるデータ環境」が自然と組織文化として根付いていきます。
「メタデータを管理したいけれど、何から実施していいかわからない」「データ分析の専門家の知見を取り入れたい」という方は、メタデータ管理構築の実績豊富な弊社、データビズラボにお気軽にご相談ください。
貴社の課題や状況に合わせて、メタデータ管理の進め方をご提案させていただきます。